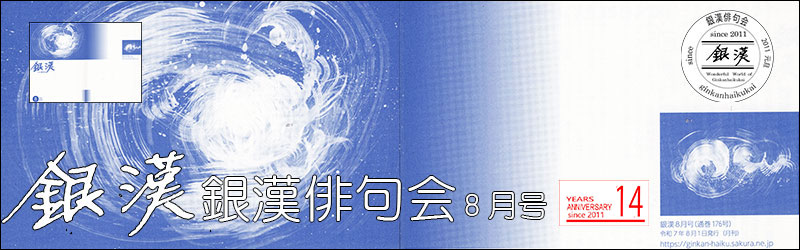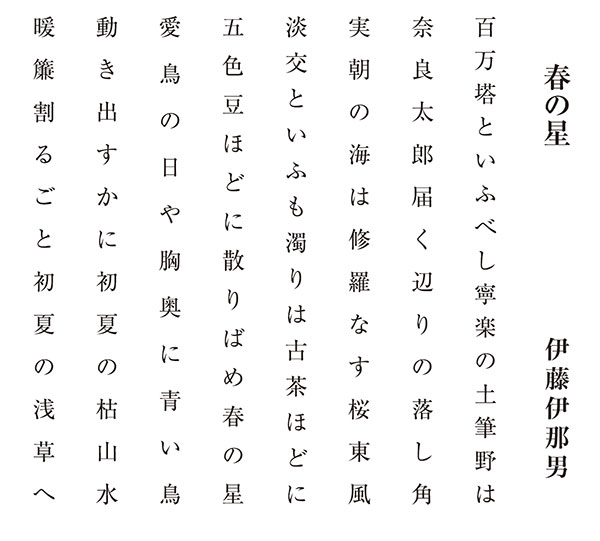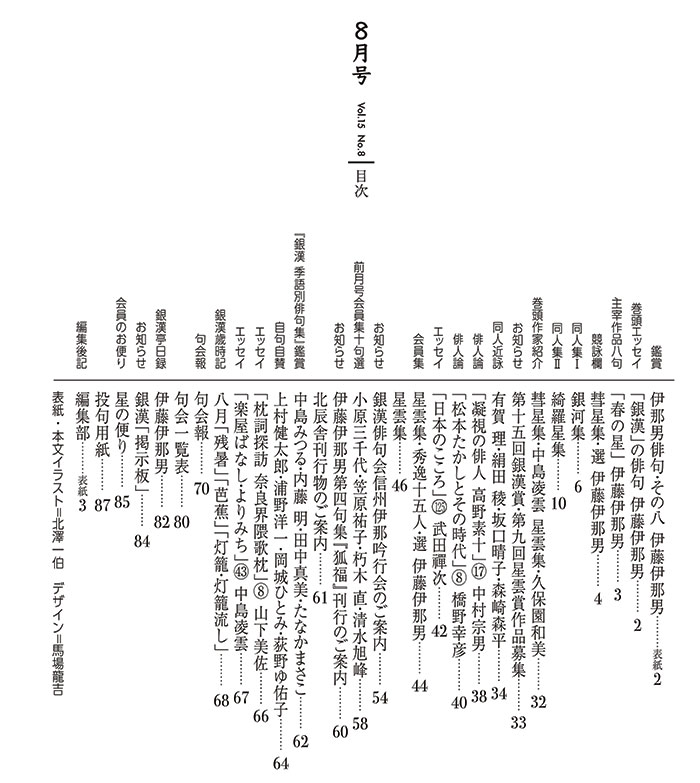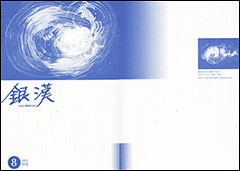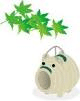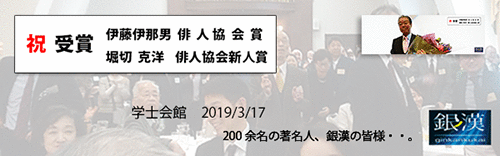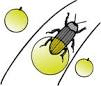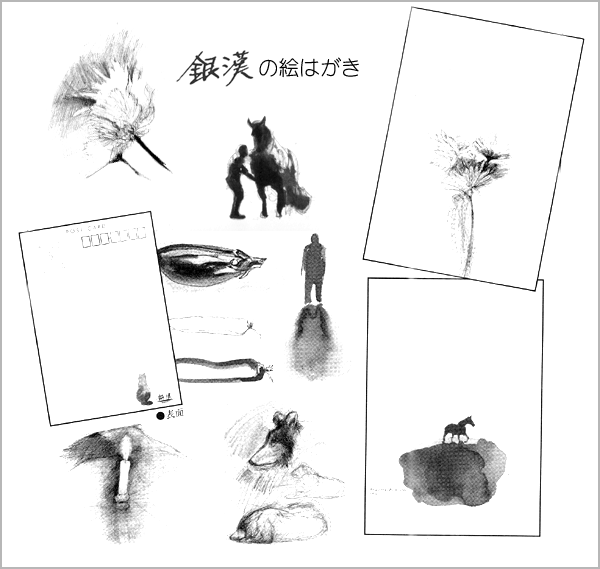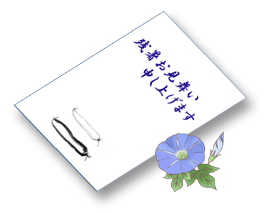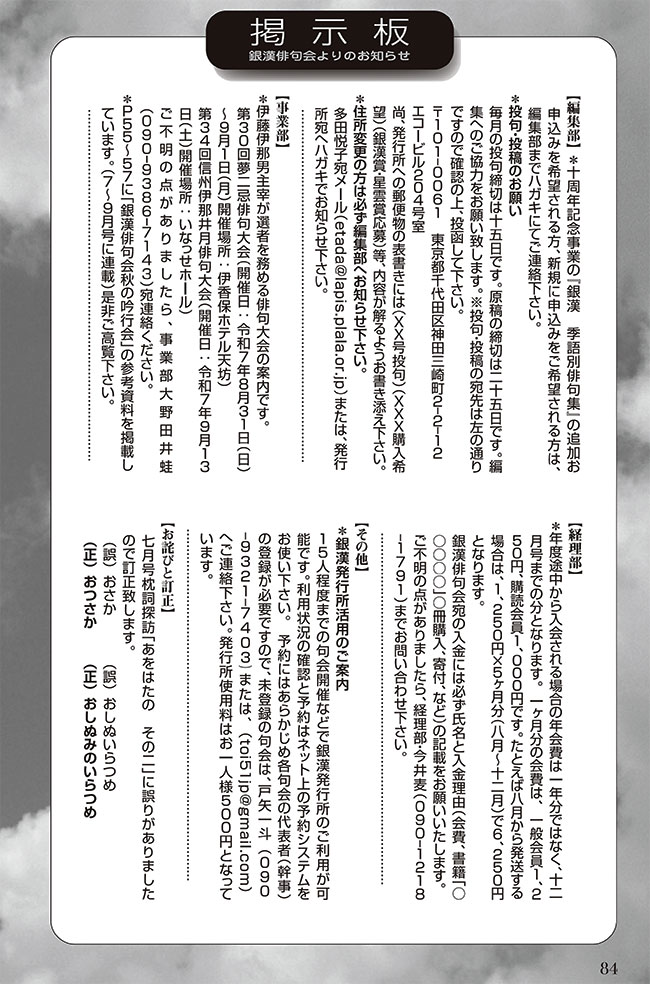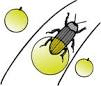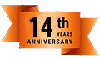銀漢の俳句
伊藤伊那男
◎秩父
秩父に通い出したのは俳句を始めて数年後、三十五歳の頃からだった。以来四十年ほどになる。一月三日、皆川盤水先生を囲む秩父吟行会に加えて貰ったのがきっかけである。秩父神社に初詣をし、十一番常楽寺で大般若経の転読の響く中、甘酒と福笹を戴く。道々獅子舞と遭遇するのが常であった。料理店で初句会に臨む。そんな会が七、八年続いたように思う。他に傾斜畑に囲まれた栃本集落や鉱泉宿での合宿もあった。
すっかり秩父の魅力に惹かれて、その後暇を得ると独りで秩父へ通うようになった。秩父夜祭も五回程見たし、両神山や二子山へ登山もした。数えてみれば五十回位は訪ねていることになる。秩父は東京からの交通の便がよく、それにもかかわらず固有の文化を堅持し、また懐かしい風景も保っている。三峰山や宝登山のような聖地もあれば、秩父三十四観音霊場もある。各地区に独特の祭や行事がある。信州の山国で育った私にとっては八方を山に囲まれたこの盆地は故郷の続きのような安心感の持てる土地である。
食べ物もいい。蕎麦の名店が幾つもある。おっ切り込みという煮込みうどんもいい。杓子菜という漬物も好きである。豚肉の味噌漬けもいい。そうそう秩父ホルモン焼も安くて旨い。足繁く訪ねた御花畑駅近くの「高砂ホルモン」は丸い穴の開いたテーブルに七輪をはめ込み、餅焼網で焼く。もうもうたる煙に巻かれながら、山盛りに置かれている生のキャベツを肉の合間にばりばりと嚙る。ここ七、八年は武田編集長の差配で、二月になると猪鍋を食べる会があった。町中にあった「桂」というその店は武田さんの念押しで、吟味された猪肉が用意されており、八丁味噌を加えた合わせ味噌の出汁が絶妙であった。私は卵と芹を持ち込んで残り汁でおじやを作ったが、好評であった。その店は二年前に閉じてしまった。今年、長瀞駅から徒歩三十分ほどの「千葉亭」という店を、またまた武田さんが見つけてくれて二十四名で訪ねた。猪肉のスペアリブなども出て、これもまた別種の趣きがあった。
西武秩父駅には隣接して温泉設備も整備され、行楽客も増えた。レッドアロー号とは別に横浜中華街への直通快速電車なども開通していて、時代の変遷に驚く。だがまだまだ秩父は四季折々訪ねて、飽きることが無い。
丹田を秩父に据ゑて牡丹鍋
猪喰うて老いの血潮を泡立てむ
兜太逝く秩父の冷えがふぐりまで
|

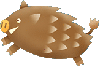



彗星集作品抄
伊藤伊那男・選
菖蒲湯の溢るるほどに明日思ふ 長谷川千何子
母の日や母の貫禄には遠く 清水佳壽美
焼鮎を縦で受け取り横に喰む 大田 勝行
競漕の岸に母校の名の谺 日山 典子
彼岸より此岸へ桜吹雪かな 長谷川明子
春火鉢顔と顔とが近すぎて 久保園和美
三山の全貌を得て麦の秋 今村 昌史
戒名に代はる本名鳥雲に 中込 精二
これ以上架けられぬまで虹の橋 曽谷 晴子
風を呑む風の申し子鯉幟 たなかまさこ
茅花ほほけ壱岐の古墳は主知れず 朽木 直
打水の玉ころげゆく神楽坂 橋野 幸彦
籐椅子に父の名残の背の窪み 伊藤 庄平
修善寺の哀史をつつむ若葉雨 塚本 一夫
白に百色赤に百色薔薇の園 島谷 高水
新茶汲む三代続く鉄瓶で 大田 勝行
尾へ走る風の脈動鯉のぼり 戸矢 一斗











銀河集作品抄
伊藤伊那男・選
神鹿の威厳のきざし袋角 東京 飯田眞理子
七島の浮き立つ伊豆の蜃気楼 静岡 唐沢 静男
豆の飯先づは仏を喜ばす 群馬 柴山つぐ子
母の日の母の戦後を語り合ふ 東京 杉阪 大和
袋角奈良の茶店の灯に寄れり 東京 武田 花果
柚口満さん送別会向島百花園
一期一会花の宴に隣る席 東京 武田 禪次
春障子立て半眼の九体仏 埼玉 多田 美記
保存会総出で送る出開帳 東京 谷岡 健彦
野焼き果てをとこ芯まで焦げくさし 神奈川 谷口いづみ
清和なるブルーインクの試し書き 長野 萩原 空木
積みて売る六法全書春暑し 東京 堀切 克洋
九品仏留守の一つや亀鳴けり 東京 三代川次郎
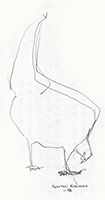



伊藤伊那男・選
卵白を角の立つまで夏初め 東京 飛鳥 蘭
旅立ちの改札口や燕の巣 東京 有澤 志峯
天水は力水なり瓜の花 神奈川 有賀 理
白鷺の腹赤く染む朱夏の朝 東京 飯田 子貢
磨かれしジョッキの光夏兆す 山形 生田 武
白雲の御神酒に浮かぶ山開 埼玉 池田 桐人
鯉幟風の止む間も眼を見張る 東京 市川 蘆舟
樹齢みな百余の杜の若葉光 埼玉 伊藤 庄平
早苗饗や写真の祖父を主とし 東京 伊藤 政
一村を月に浮かべる代田の夜 神奈川 伊東 岬
初虹や旅に湖国の城行けば 東京 今井 麦
指先の黒ずむほどに蕗の嵩 埼玉 今村 昌史
嚙み締むる塩の甘みや豆の飯 東京 上田 裕
屋根裏にまむし酒あり遺品なり 東京 宇志やまと
開帳や千体仏の小さきこと 埼玉 大澤 静子
客発ちて宿の風鈴静かなり 神奈川 大田 勝行
追憶の縁よりこぼれ春落葉 東京 大沼まり子
五月来る客船百の窓に海 神奈川 大野 里詩
月山の月を頼りに張る田水 埼玉 大野田井蛙
七重八重影を重ねて牡丹かな 東京 大溝 妙子
つくづくと芳しき葉よ柏餅 東京 大山かげもと
聴くうちに聞き分けてをり愛鳥日 東京 岡城ひとみ
あんぱんの胸に閊へて花の昼 愛知 荻野ゆ佑子
森の奥のお菓子の家へ春ともし 宮城 小田島 渚
道に海胆置いて割らせる島鴉 宮城 小野寺一砂
蜃気楼幽霊船のひいふうみ 埼玉 小寺 清人
身を畳む時の力や尺取虫 和歌山 笠原 祐子
母ならぬ自分にも買ふカーネーション 東京 梶山かおり
舌先の尖つてをりぬ冷奴 愛媛 片山 一行
鍛冶町の角の仕舞屋祭笛 東京 桂 説子
明日葉や畑に積る火山灰 静岡 金井 硯児
重力のままハンカチの花咲けり 東京 我部 敬子
泉湧く谷戸の木漏れ日揺らしつつ 東京 川島秋葉男
茣蓙畳む落花四角に切取りて 千葉 川島 紬
陰干しの芭蕉布舞へば三線が 神奈川 河村 啓
大瑠璃のこゑや山路を急がせり 愛知 北浦 正弘
豌豆のつるの行方や青い空 東京 北川 京子
蛙の夜旅の鞄を肩にかけ 長野 北澤 一伯
義理立ての席空く東をどりかな 東京 絹田 稜
薇のほどけぬ内の酢味噌和へ 東京 柊原 洋征
これほどに低き教卓啄木忌 東京 朽木 直
譬ふれば推歩先生遅桜 東京 畔柳 海村
猫のかげ過ぎしと思ふ朧かな 東京 小泉 良子
春日傘北鎌倉で降りにけり 神奈川 こしだまほ
制服の汚れ無き白夏初め 東京 小林 美樹
愛鳥週間不思議に鳥の集まる樹 千葉 小森みゆき
武者凧の尾の絡むまま戦へり 東京 小山 蓮子
相席に鰹追ひ来し土佐の人 宮城 齊藤 克之
日溜りのやうな母居て母の日よ 青森 榊 せい子
霾や元寇の島塩を売る 長崎 坂口 晴子
麦笛のその音までも青臭し 長野 坂下 昭
通学児の挨拶ほめて朝桜 群馬 佐藤 栄子
湖の風のやはらか閑古鳥 群馬 佐藤かずえ
起きぬけに仰ぐ城址や夏来る 長野 三溝 恵子
青き海掬へば無色夏初め 東京 島 織布
二人乗り自転車でゆく愛鳥日 東京 島谷 高水
紫の闇の大原紫蘇畑 兵庫 清水佳壽美
本降りとなりたる音に朝寝かな 東京 清水 史恵
葉桜の風に騒めく夕つ方 東京 清水美保子
桜湯や白ネクタイも久しぶり 埼玉 志村 昌
散髪に仕上ぐる祭支度かな 千葉 白井 飛露
藤の花百花違はず指す地軸 神奈川 白井八十八
薪能業の深きが吾の影に 東京 白濱 武子
子等来る皆柏餅手土産に 東京 新谷 房子
桜鯛澄みし目のまま皿の上 大阪 末永理恵子
うららかや誰の法事か忘れをり 岐阜 鈴木 春水
麦笛は故郷の音のひとつかな 東京 鈴木 淳子
佐保姫のひと振りに咲く野辺の花 東京 鈴木てる緒
土筆茹で生命の明かり戴けり 群馬 鈴木踏青子
仔馬はや雨風耐へる心意気 東京 角 佐穂子
濡れ縁に足を投げ出し春惜しむ 東京 関根 正義
柔らかきままのてつぺん袋角 埼玉 園部あづき
暁に轟く羽音バードデー 埼玉 園部 恵夏
白シャツを空に張り付くやうに干す 奈川 曽谷 晴子
蝌蚪生る水田に沼に五線紙に 長野 髙橋 初風
静寂を花に集めて白牡丹 東京 高橋 透水
春の夜を抜きて喪服の躾糸 東京 武井まゆみ
いづくから眠気誘ふ河鹿笛 東京 竹内 洋平
誰が便りポストに入る夏の蝶 東京 竹花美代惠
蛍烏賊千のひかりを放ちたる 神奈川 田嶋 壺中
地球儀の埃そのまま霾ぐもり 東京 多田 悦子
青紫蘇の風に香の立つそば処 東京 立崎ひかり
霾や墨絵のごとく滲みをり 東京 田中 敬子
薄れゆく母の記憶や春の虹 東京 田中 道
冷奴一人頼めば皆頼む 東京 田家 正好
春の夜の魔法のランプ磨く夢 東京 塚本 一夫
街路樹も色濃くなりぬ更衣 東京 辻 隆夫
更衣せぬ暮しにも慣れにけり ムンバイ 辻本 芙紗
あやふやにややそれなりに更衣 東京 辻本 理恵
シャンパンの天使の吐息春の宵 愛知 津田 卓
大仏の背に顔出す遠足児 東京 坪井 研治
切株にしばし休むもみどりの日 埼玉 戸矢 一斗
新語より死語に親しき昭和の日 千葉 長井 哲
行く春や長さの違ふ夫婦箸 東京 中込 精二
哭き龍といふべきものも涅槃図に 大阪 中島 凌雲
雲に入る中仙道や朴の花 東京 中野 智子
開闢の空の奥より五月来ぬ 東京 中村 孝哲
桜湯の八重にほどけて香るかな 茨城 中村 湖童
あけたての音やはらかき春障子 埼玉 中村 宗男
春昼やあんぱんにのる芥子の粒 東京 中村 藍人
木曾谷が膨る筍流しかな 長野 中山 中
故郷を出づ逃水を追ふごとく 千葉 中山 桐里
花吹雪蹴速の塚の散華とも 大阪 西田 鏡子
もう影を持たぬ高さに夏の蝶 埼玉 萩原 陽里
遠足の帰りの歩幅揃はざる 東京 橋野 幸彦
座布団に猫の温みや昭和の日 広島 長谷川明子
花冷や胸にをさむることふえし 東京 長谷川千何子
散る花に歓声上がる句碑開き 兵庫 播广 義春
開帳仏あはき日にさへおん眼伏せ 埼玉 半田けい子
母の日や母をいくたび泣かせしか 埼玉 深津 博
花吹雪浴びて光陰惜しみけり 東京 福原 紅
駅毎に心に刻む若葉寒 東京 星野 淑子
岐阜蝶の過るひかりの数珠となり 岐阜 堀江 美州
次次に飛び出すティッシュ復活祭 埼玉 本庄 康代
「おたたさん」と呼ばるる老いし穴子売 東京 松浦 宗克
母の日や糸の通らぬ針の穴 東京 松代 展枝
夫婦仲良き和菓子屋の桜餅 神奈川 三井 康有
その中に血の脈打てり袋角 神奈川 宮本起代子
二人静山恋ふるかに蕊を寄せ 東京 村田 郁子
母の日や母を探して鏡拭く 東京 村田 重子
花吹雪ならば遭難するもよし 東京 森 羽久衣
山薄暑丸太二本で渡る沢 千葉 森崎 森平
不滅の火うちに灯して山笑ふ 埼玉 森濱 直之
水平といふ心地良き代田かな 長野 守屋 明
鳴き龍にいとま取らせぬ遠足子 東京 矢野 安美
リルケにはほどとほきかな吾が春愁 愛知 山口 輝久
気疲れの多き仏事や花辛夷 群馬 山﨑ちづ子
直会にこぞりて桜吹雪かな 東京 山下 美佐
大津絵の鬼と目が合ふ五月闇 東京 山田 茜
生涯を生家に遠く桐の花 東京 山元 正規
波音や余呉湖に開くる春障子 東京 渡辺 花穂


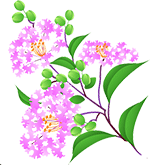


銀河集・綺羅星今月の秀句
伊藤伊那男・選
今回はお休み致します。





伊藤伊那男・選
秀逸
深更の妻子の寝息桜桃忌 東京 南出 謙吾
水底に影を走らせみづすまし 神奈川 西本 萌
牡丹の雀色時こらへ時 東京 尼崎 沙羅
よろこびの数ほど咲けり犬ふぐり 広島 小原三千代
夕さりの沼の死角や亀鳴ける 栃木 たなかまさこ
晩年を生きて夕べの桜かな 静岡 橋本 光子
水浴びに転がり入るや雀の子 千葉 平山 凛語
浅間山より高く上がれと鯉のぼり 群馬 横沢 宇内
花ことば希望と聞きし種を蒔く 埼玉 梅沢 幸子
牛追ひの鞭やはらかき夏野かな 東京 髙城 愉楽
二煎目の香りまだまだ新茶かな 東京 熊木 光代
麦笛や見やう見まねの音合せ 長野 桜井美津江
夏めくや雲梯の子の力瘤 東京 幕内美智子
畦川を跳んで陽炎見失ふ 埼玉 水野 加代
みちのくの風は眩しき五月かな 東京 家治 祥夫

星雲集作品抄
伊藤伊那男・選
雪崩過ぐ森閑として空青し 東京 飯田 正人
春深し仏でさへも半眼に 東京 井川 敏
その年に植ゑし桜や洪水碑 長野 池内とほる
蕗の葉の下の小人や今いづこ 東京 石床 誠
紙飛行機もつと遠くへ夏の空 東京 一政 輪太
うら若き脈潜みたり袋角 東京 伊藤 真紀
朧夜の電話に兆す思郷かな 広島 井上 幸三
肘枕してふるさとの初蛙 長野 上野 三歩
雨降りの前に掃かねば松落葉 長野 浦野 洋一
竹の子を掘る鍬もなく蹴とばせり 静岡 大槻 望
単線の窓に数へる鯉のぼり 東京 岡田 久男
老鶯の乱調気味や獣道 静岡 小野 無道
青楓影を作れる薄茶席 群馬 小野田静江
山麓を一段ごとに田水張る 埼玉 加藤 且之
麦笛を聴く道草や土手すべり 長野 唐沢 冬朱
富士山に農鳥の浮く田植どき 東京 軽石 弾
花吹雪散骨を見るごときかな 愛知 河畑 達雄
マネキンの服の薄さや夏来る 東京 北原美枝子
ヴェネツィアの茹で蛸赤し路狭し 東京 久保園和美
雨の日であればまた会ふかたつむり 群馬 黒岩あやめ
散り急ぐ観音堂の遅桜 群馬 黒岩伊知朗
青楓枯山水に波打ちぬ 愛知 黒岩 宏行
遠き日の父のため息竹落葉 東京 髙坂小太郎
負けまいぞすててこのゴム強く締め 神奈川 阪井 忠太
山藤や傾るる如く風誘ふ 東京 佐々木終吉
鯉のぼり浅間の風を待ちてをり 群馬 佐藤さゆり
忘れものした心地なる晩夏かな 東京 島谷 操
わが窓に花の一世や飛花落花 千葉 清水 礼子
榛名路に始まりにけり代田搔き 群馬 白石 欽二
葉脈の旨味しみじみ柏餅 東京 須﨑 武雄
花びらに光の玉や牡丹咲く 愛知 住山 春人
今日もまた薬数へし薬の日 東京 田岡美也子
また同じ本を購ふ薄暑かな 東京 寳田 俳爺
暗闇に御輿を担ぐ祭かな 埼玉 武井 康弘
鞦韆を揺らして思ふ遠き日々 広島 藤堂 暢子
家族皆贔屓のありし金魚かな 埼玉 内藤 明
青空を透かす葉陰に梅実る 神奈川 長濱 泰子
曳山を送る名残の桜かな 京都 仁井田麻利子
日に透けて身籠る目高藻の中へ 東京 西 照雄
つき指の元に戻りて山笑ふ 宮城 西岡 博子
瓜刻む音は変はらず母の家 東京 西田有希子
麗かや二両列車に客一人 東京 橋本 泰
五月憂し明日は必ず美容院 神奈川 花上 佐都
代田なか生家鏡に浮かぶごと 長野 馬場みち子
をさな児の肌に湯の散る菖蒲風呂 千葉 針田 達行
春雪を追ひし回転木馬かな 神奈川 日山典子
檀林の音なき風や白牡丹 千葉 平野 梗華
別れ雪と思ひつ三度今日も又 長野 藤井 法子
鯖寿司や一年振りの三回忌 福岡 藤田 雅規
猫が耳舐める仕草や梅雨近し 栃木 星乃 呟
浅蜊吹く厨の流し飛び越えて 東京 松井はつ子
惜しきほどこぼれ落つるや柿の花 愛知 箕甫 佐子
翡翠の碧き弾丸橋二つ 東京 宮下 研児
少しづつくたびれてをり夏背広 東京 無聞 益
満山の色愛しむや若葉風 宮城 村上セイ子
花筏分けし小舟の櫓を止める 神奈川 山田 丹晴
花冷や客の帰りて居間広し 静岡 山室 樹一
新緑に仁王阿吽の息深く 神奈川 横地 三旦
若葉風揺るるものみな透き通る 神奈川 横山 渓泉
食卓にカーネーションと一筆箋 千葉 吉田 正克
貴船川床泳ぐ形に鮎の出 東京 若林 若干
三椏の花の盛りの長きこと 東京 渡辺 広佐
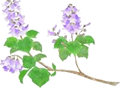




星雲集 今月の秀句
伊藤伊那男
今回はお休み致します。
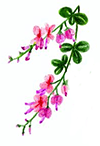




伊那男俳句 その八(令和七年八月号)
蛇穴を出て関節を鳴らすらむ
蛇が苦手である。妻と喧嘩をした時に「あなたなんて寝てる間に布団の中に蛇をいれたらショックで死んじゃうんだから」と言われて心から恐怖を感じた。長女と上野動物園に行った時の作文で「父は蛇舎の前で顔が真青になって動けなくなりました」と書かれてしまった。だが怖い物見たさで蛇の句は幾つもある。〈蛇穴に入り松籟の募り初む〉〈湯殿山蛇安心の舌出せり〉〈くちなはの消えてにはかになまぐさし〉〈蝮酒二日ほどして少し効く〉〈端正なとぐろでありぬ蝮酒〉など。自分で言うのも厚かましいがまずまずの句である。小学生の頃、学校に住み込みの用務員さんの住宅によく遊びに行った。ある時七輪の餅焼網の上に五㎝位の真白いものが蠢いていた。それは皮を剝いてぶつ切りにされた蛇であった。それ以後、用務員さんの住宅を訪ねたことは無かった。蛇嫌いはそこから始まったのか、もっと潜在的な、DNAに組み込まれたものであったのか……。平成二十三年作『然々と』所収
|





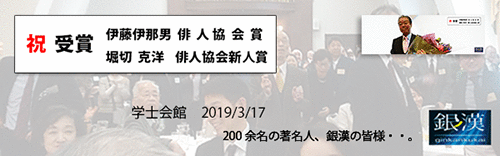
更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。



リンクします。
aishi etc




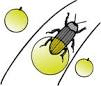
挿絵が絵葉書になりました。
Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組
8枚一組 1,000円
ごあいさつにご利用下さい。
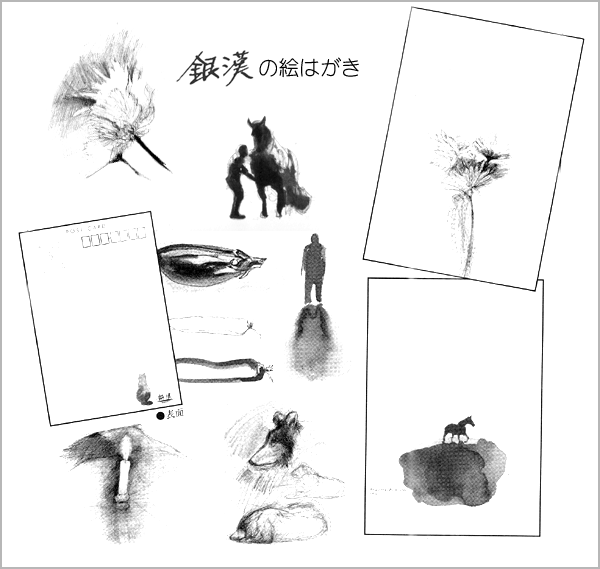
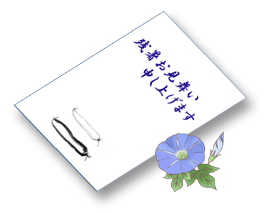





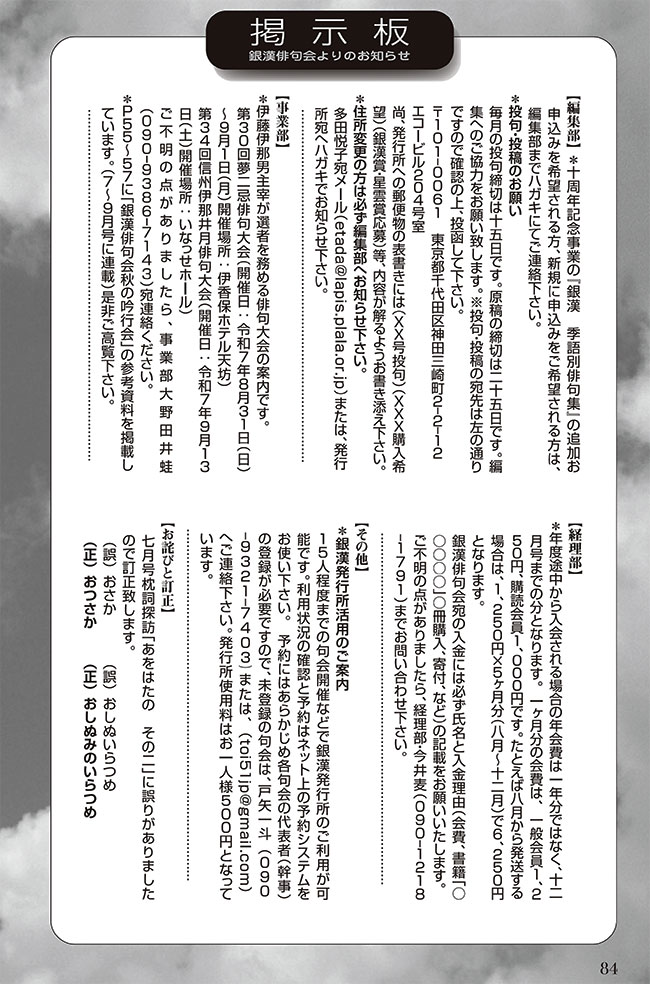






|
![]()
![]() 8月号 2025年
8月号 2025年